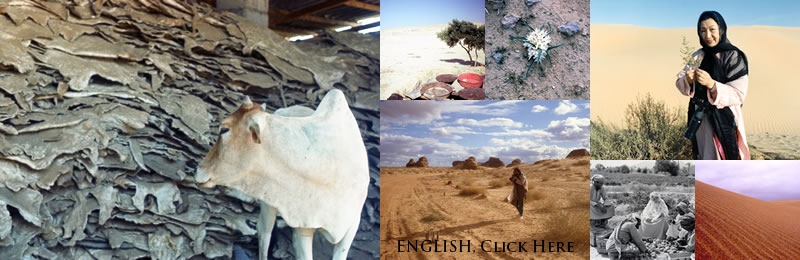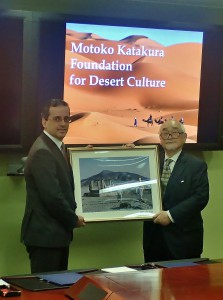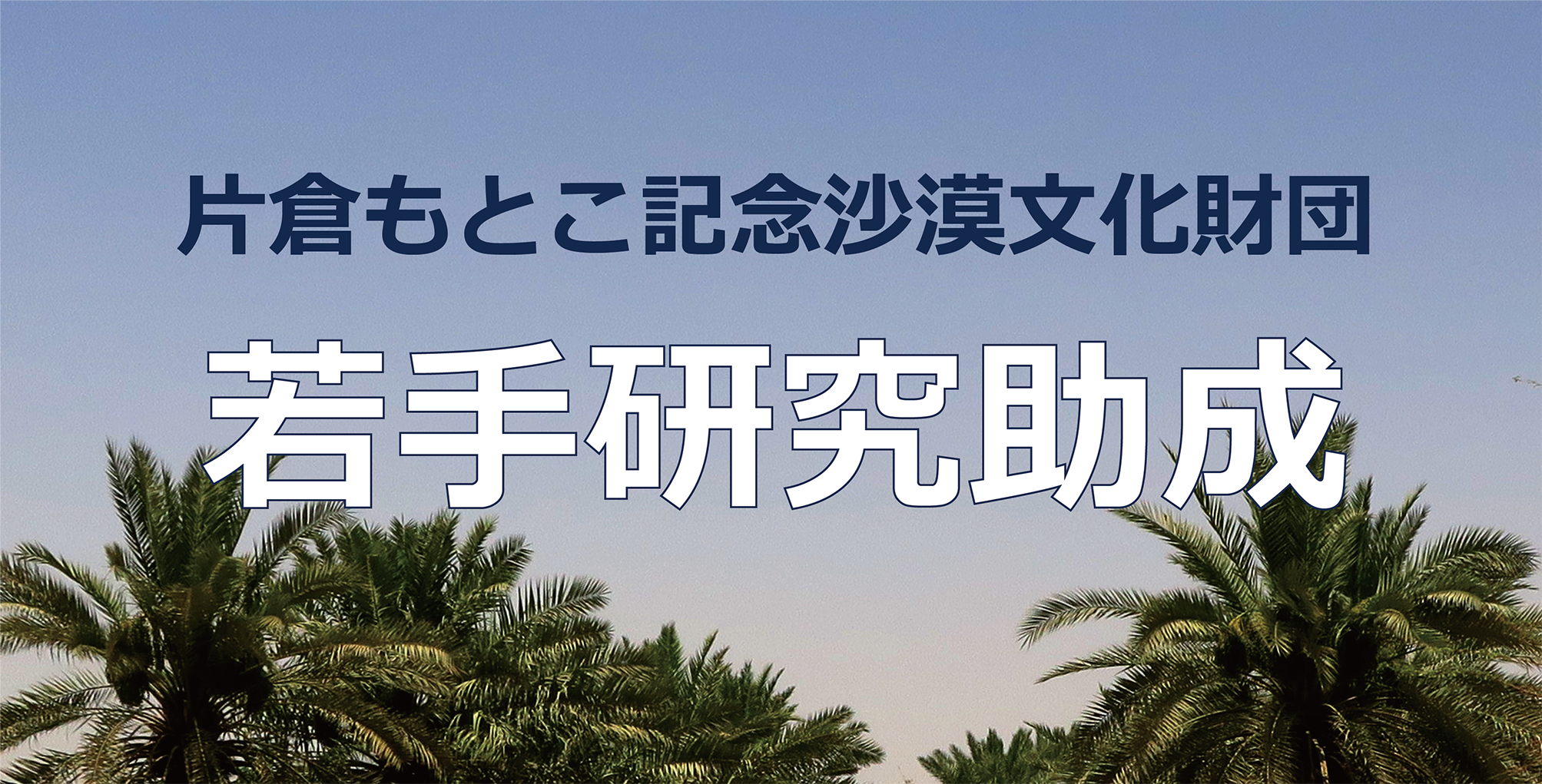2015年7月8日、縄田浩志理事が、2015年度(第30回)大同生命地域研究奨励賞を受賞しました。
大同生命地域研究奨励賞は、「地球的規模における地域研究」の分野において、新しい展開を試み、今後さらなる活躍が期待される研究者に対して贈呈される賞です。
片倉もとこも、1991年度「アラブ・イスラーム研究の新境地開拓の業績」に対して同賞を受賞しています。

7月24日、贈呈式がクラブ関西(大阪市)にて開催されました。

受賞スピーチをおこなう縄田浩志理事
今回の受賞は、縄田理事がこれまで取り組んできた「中東・北東アフリカにおける未来志向型の地域研究とアラビア語による出版を通じた研究資源の共有化」に対して贈られました。
縄田理事は、スーダン紅海沿岸の地域住民の生業(なりわい)に重点を置いた研究をはじめ(学位論文「乾燥地帯の沿岸域における人間・ヒトコブラクダ関係の人類学的研究-スーダン東部、紅海沿岸ベジャ族における事例分析から」2003年、京都大学)、北アフリカ、中東地域の熱帯・乾燥地域において、地域住民が培ってきた在来知をもとに環境へ適応、生産活動を行ってきたことを丁寧に明らかにし、「ポスト石油時代」に向けた多様な生物資源管理の学術的基盤を提示してきました(総合地球環境学研究所プロジェクト「アラブ社会におけるなりわい生態系の研究-ポスト石油時代に向けて」2008-2013年)。
さらに、日本語・英語のみならず、特にアラビア語で研究成果を出版したことで「地域と社会的還元に多大な貢献を果たした」として、研究資源を国内外で広く共有する姿勢が大いに評価されました。
詳しくは、大同生命国際文化基金のWEBサイトからご覧いただけます。